いろいろなお茶の種類
お茶の種類(分類)
お茶は茶葉を摘み取った直後に熱を加えて発酵を止めるか、また若干発酵させた後に熱を加えて発酵を止めて加工するか、もしくは完全に発酵させた後に加工するかで大まかに3種類のお茶に分類されます。
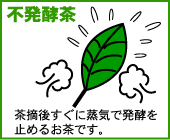
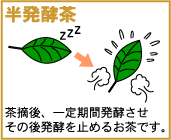

 玉露・かぶせ茶
玉露・かぶせ茶
新芽が開き始めた頃に「よしず棚」などで日光を遮りうまみ成分のテアニンを増やすためコクと甘みのある味わいが特徴です。 「かぶせ茶」は玉露と似た製法ですが遮光期間が短いお茶です。
 煎茶・深蒸し茶
煎茶・深蒸し茶
流通量の85%を占め最もよく飲まれているのが煎茶です。爽やかな香りと程よい渋みが特徴です。深蒸し茶は普通煎茶より長い蒸し時間で仕上た煎茶で一般に香りは弱めですが濃厚な味わいが特徴です
 番茶
番茶
夏や秋摘みの採取時期が遅い煎茶を番茶といいます。夏の強い日差しを浴びている為、渋み成分を比較的多く含みます。
 ほうじ茶
ほうじ茶
番茶や煎茶を強火で焙煎したお茶です。香ばしい香りとすっきりとした味わいが特徴です。葉を主体とした「ほうじ茶」と茎を主体とした「茎ほうじ茶」があります。![]()
![]()
![]()
 玄米茶
玄米茶
番茶や煎茶に玄米をブレンドした煎茶の香りと玄米の香りの調和したお茶です。さらに抹茶をブレンドした抹茶入り玄米茶は玄米の香りに加え抹茶の味わいとコクも楽しめるので人気があります

抹茶
玉露と同様、日光を遮って育てた若葉を乾燥させた「碾(てん)茶」というお茶から茎や葉脈を取り除いた後、石臼などでひいて粉状にしたお茶です
 玉緑茶
玉緑茶
最後の工程が煎茶と違い形を整える工程を省いたため丸みを帯びた形状に仕上がっているのが特徴です。蒸製の玉緑茶のほかに鉄製の釜で炒る中国式の玉緑茶もあります。

烏龍茶(ウーロン茶)など
発酵を止めた緑茶と完全発酵した紅茶の中間に位置する半発酵仕上げのお茶の代表が烏龍茶です。福建省、広東省、台湾などが代表産地です。

紅茶
茶葉を完全に発酵させて仕上ると紅茶になります。紅茶は全世界で生産されている茶の80%を占め代表産地はインド、スリランカなどです。
日本各地のお茶の産地
お茶の木は寒さに弱いため比較的温暖で適度な降水量のある地域で生産されています。
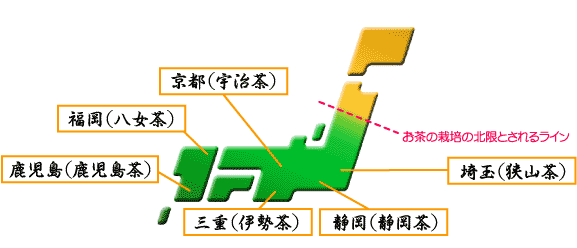
茶畑から製品まで、お茶の製造工程

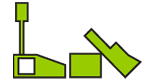
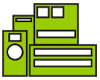
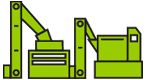
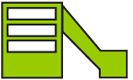
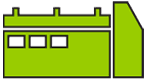
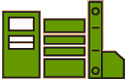
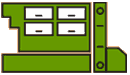

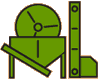
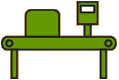
【1】茶畑・茶摘
毎年、5月上旬(八十八夜前後)お茶の葉は手摘みや茶摘機などで摘み取られ荒茶工場へ運ばれます。
【2】給葉機・蒸機・冷却機
茶畑から集められた茶は給葉機によって自動的に蒸機へ送られ蒸気で蒸します。その後、冷却機によって水分を取り除きながら茶葉を冷やしていきます。
緑茶が「不発酵茶」と呼ばれるのはここで蒸気による加熱で発酵を止めるからです。
【3】粗揉機
強い力で揉みながら熱風を当て水分を減らします。
【4】中揉機・揉捻機
茶の葉を再び揉みながらさらに熱風を当てます、その後揉捻機で茶の葉に力を加えて水分の均一をはかりながら揉みます。
何度も繰り返し熱を加えて徐々に水分を減らしていきます。
【5】精揉機
茶の葉に熱を加え更に水分を落とし力を加え形を整えます。
【6】乾燥機
揉みあげた茶を更に念入りに乾燥させます。
ここまでが「荒茶製造工程」となり、この時点の茶葉は「荒茶」と呼ばれます。
【7】総合仕上機
荒茶は形が大小様々な状態で混じり合っているので、ふるい分けや切断などして形を整えきれいにしていきます。
【8】仕上茶乾燥機
茶を、さらによく乾燥させると同時に独特のお茶の味やかおりを引き出します。【7】総合仕上機と【8】仕上茶乾燥機での技術がお茶の香りや味わいに大きく影響します。
【9】選別機
木茎や細かい茎を取り除きます。
【10】合組機
製品の最終調整のため配合と均一化をはかります。
ここまでが「仕上茶製造工程」となり、この時点の茶葉は「仕上茶」と呼ばれます。
【11】計量・検査・包装
合組機から取り出されたお茶は計量された後、品質検査を経て包装されます。
【12】製品完成
こうして幾度も手間をかけて仕上げたお茶が皆様のもとへと参ります。


